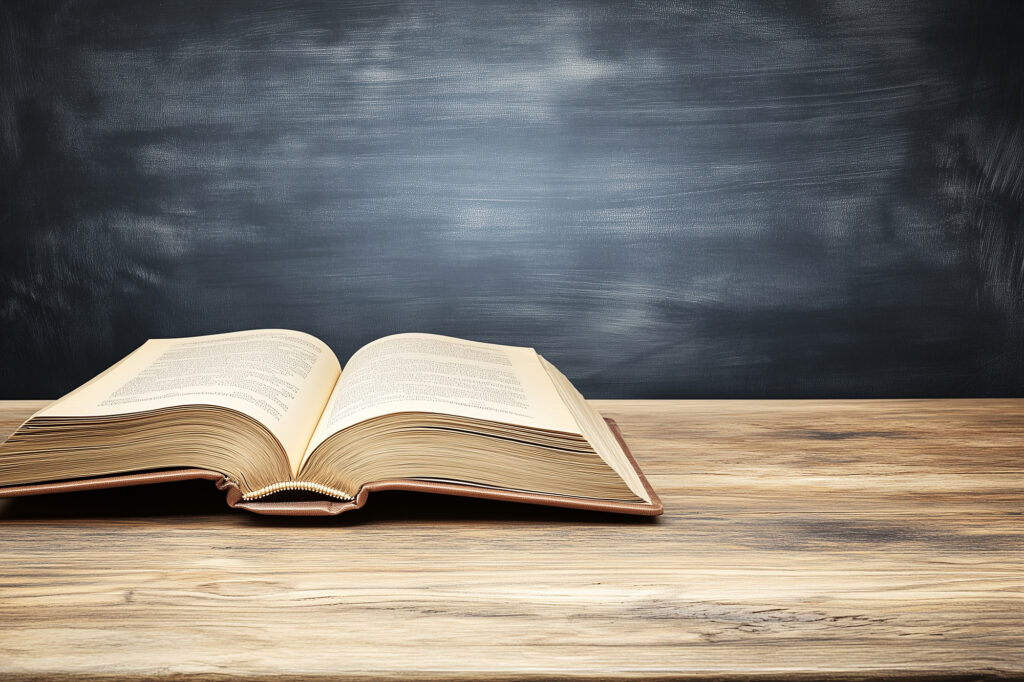共通テスト情報って何?親が知っておきたい新科目の内容と対策法
目次
共通テスト情報科目とは何か
2025年度から大学入学共通テストに新たに加わった「情報」科目について、多くの保護者が疑問を抱いています。この新しい科目は、これからのデジタル社会を生きる子どもたちにとって重要な能力を測るものです。プログラミングやデータサイエンスなど、現代社会で必要とされるスキルが評価対象となります。
情報科目が導入された背景
Society 5.0と呼ばれる超スマート社会の到来により、日本は急速にデジタル化が進んでいます。政府は2030年までにデジタル人材を230万人育成する目標を掲げており、その一環として情報教育の充実が図られています。
従来の教育では対応できない新しい課題に対処するため、文部科学省は小学校から高等学校まで段階的に情報教育を強化してきました。その集大成として、大学入試においても情報科目が必修化されることになったのです。
これは単なる教育改革ではなく、日本の国際競争力向上を目指した国家戦略の一部です。諸外国では既にプログラミング教育が当たり前となっており、日本も遅れを取り戻すべく本格的に動き出しています。
子どもたちが将来社会で活躍するためには、従来の読み書きそろばんに加えて、デジタルリテラシーが第4の基礎スキルとして位置づけられています。
共通テスト情報の出題範囲
共通テスト情報では、高等学校の必履修科目「情報Ⅰ」の内容が出題されます。具体的には以下の4つの分野から構成されています。
情報社会の問題解決では、身の回りの問題をコンピュータやデータを活用して解決する思考力が問われます。単純な暗記ではなく、論理的思考力と創造性が重要となります。
コミュニケーションと情報デザインでは、情報を効果的に伝えるための技術やメディアリテラシーが評価されます。SNSやウェブサイトでの情報発信が日常化した現代において、極めて実用的な内容です。
コンピュータとプログラミングでは、アルゴリズムの理解やプログラミング的思考が中心となります。実際にコードを書く技術よりも、問題を分解して順序立てて解決する能力が重視されます。
情報通信ネットワークとデータの活用では、インターネットの仕組みやビッグデータの活用方法、情報セキュリティについて幅広く扱われます。
従来の科目との違い
これまでの大学入試では、主に暗記力や計算力が重視されてきました。しかし情報科目では、知識を活用して新しい問題を解決する応用力が問われます。
例えば数学では公式を覚えて計算することが中心でしたが、情報科目では与えられた条件から最適解を導き出すプロセスが重要です。答えが一つではない問題も多く、創造性と論理性の両方が求められます。
また、個人での学習よりも協働学習の要素が強く、他者とのコミュニケーションを通じて問題解決を行う能力も評価されます。これは将来の職場環境を想定した、より実践的なスキルと言えます。
従来の受験勉強のように、参考書を読んで問題集を解くだけでは対応が困難な科目です。日常生活の中でデジタル技術に触れ、試行錯誤を重ねることが最も効果的な学習方法となります。
幼児期から始めるデジタルリテラシー教育
デジタル機器に囲まれて育つ現代の子どもたちにとって、適切なデジタルリテラシー教育は必要不可欠です。0歳から6歳という幼児期は、将来の学習基盤を築く黄金期とも言える重要な時期です。この時期に適切な関わり方をすることで、将来の共通テスト情報科目への対応力も自然と身につけることができます。
年齢別デジタル教育の進め方
0-2歳の時期では、デジタル機器そのものよりも、観察力と好奇心を育むことが重要です。身の回りの現象に「なぜ?」「どうして?」という疑問を持つ習慣を作りましょう。
例えば、スマートフォンのライトが点いたり消えたりする様子を見せながら、「明るくなったね」「暗くなったね」と声をかけることで、原因と結果の関係を意識させることができます。
この時期は画面を見る時間を制限し、実際の体験を通じて五感をフル活用することが大切です。積み木やブロックなどのアナログな玩具を使って、空間認識能力や論理的思考の基礎を育みましょう。
3-4歳の時期では、簡単なパズルアプリや知育アプリを活用できるようになります。ただし、一日30分以内という時間制限を設けることが重要です。
5-6歳の時期では、より高度な思考を促すアクティビティが可能になります。順序立てて物事を考えるアルゴリズム的思考を遊びの中で自然と身につけさせることができます。
家庭でできる簡単な取り組み
日常生活の中で実践できる簡単な取り組みをご紹介します。特別な教材や高価な機器は必要ありません。
お手伝いの順序化は最も手軽で効果的な方法です。「まず手を洗って、次にエプロンをつけて、それから野菜を切る」というように、作業の手順を明確に示すことで、プログラミング的思考の基礎を育むことができます。
宝探しゲームでは、「リビングの赤い箱の中」「キッチンの引き出しの奥」など、具体的な条件指定を使って遊びます。これは情報検索の基本概念を学ぶことにつながります。
分類遊びでは、おもちゃを色別、大きさ別、種類別に分けることで、データ整理の感覚を身につけます。最初は単純な分類から始めて、徐々に複雑な条件で分類できるようにしていきましょう。
親子で一緒に取り組むことで、子どもの成長を実感でき、親自身もデジタルリテラシーについて学ぶ良い機会となります。
注意すべきポイント
幼児期のデジタル教育では、いくつかの注意点があります。最も重要なのは、バランスを保つことです。
デジタル機器の使用時間は年齢に応じて適切に制限し、実体験を重視することが大切です。画面の中の世界だけでなく、実際に手で触れ、五感で感じる体験を豊富に提供しましょう。
また、子ども一人でデジタル機器を使わせるのではなく、必ず大人が一緒に使うことが重要です。適切なコンテンツを選び、子どもの反応を観察しながら進めることで、より効果的な学習が可能になります。
完璧を求めすぎないことも大切です。子どもの発達には個人差があり、無理に進めると逆効果になる場合もあります。子どものペースに合わせて、楽しみながら学習できる環境を整えることが最も重要です。
プログラミング的思考の育て方
プログラミング的思考とは、コンピュータープログラムを書く技術のことではありません。問題を分析し、手順を整理し、効率的な解決方法を見つけ出す思考プロセスのことです。この思考力は共通テスト情報科目において非常に重要であり、幼児期から日常生活の中で自然と育むことができます。
論理的思考力を伸ばす遊び
積み木やブロック遊びは、プログラミング的思考を育む最も効果的な方法の一つです。子どもは試行錯誤を重ねながら、安定した構造を作り上げるために順序やバランスを考えるようになります。
最初は自由に積み上げるだけでも構いませんが、徐々に「どうしたらもっと高く積めるかな?」「どんな順番で積んだら倒れないかな?」といった問いかけをしてみましょう。
パズル遊びでは、分解と統合の概念を学ぶことができます。大きな問題を小さな部分に分けて考え、最終的に全体を完成させるプロセスは、まさにプログラミング的思考そのものです。
年齢に応じて適切な難易度のパズルを選び、完成したときには一緒に喜びを分かち合うことで、達成感と継続意欲を育むことができます。
料理のお手伝いは、レシピというアルゴリズムに従って作業を進める実践的な学習機会です。「まず材料を準備して、次に切って、それから炒める」という手順を守ることで、順序立てて考える力が自然と身につきます。
問題解決能力の基礎作り
日常生活の中で起こる小さな問題を、子どもと一緒に解決していくことが重要です。「どうしたらいいかな?」という問いかけから始めて、子ども自身に考えさせる時間を作りましょう。
例えば、おもちゃが片付かない時に「どうしたら早く片付けられるかな?」と問いかけます。子どもが「同じ種類を集める」「箱を使い分ける」などのアイデアを出したら、実際に試してみて結果を確認します。
この過程で、仮説を立てる→実験する→結果を検証するという科学的思考法も身につけることができます。失敗しても「次はどうしたらいいかな?」と前向きに捉える姿勢を大切にしましょう。
「なぜ?」を大切にすることも重要です。子どもの質問に対して、すぐに答えを教えるのではなく、「どうしてそう思うの?」「他にも理由があるかな?」と逆に問いかけることで、深く考える習慣を育むことができます。
親が答えを知らない質問でも、一緒に調べたり実験したりすることで、学習する楽しさを共有することができます。
創造性を育む環境づくり
プログラミング的思考には、創造性も重要な要素です。決まった答えがない問題に対して、独創的なアプローチを考える能力を育てることが大切です。
自由工作の時間を定期的に設けて、子どもの発想を制限しない環境を作りましょう。廃材や自然素材を使って、何でも自由に作らせてあげることで、発想力と実現力の両方を育むことができます。
「正解」にこだわらないことも重要です。大人の価値観で「間違い」と判断せず、子どもなりの論理や発想を尊重することで、自信とチャレンジ精神を育むことができます。
多様な体験を提供することで、発想の引き出しを増やすことも大切です。美術館、科学館、自然体験など、様々な場所で新しい刺激を受けることで、柔軟な思考力が育まれます。
失敗を恐れずに挑戦できる安心できる環境を整えることで、子どもは自由に発想し、実験し、学習することができるようになります。
情報リテラシーと安全なインターネット利用
現代の子どもたちは「デジタルネイティブ」と呼ばれ、生まれた時からデジタル機器に囲まれて育っています。しかし、デジタル技術を使えることと、適切に活用できることは全く別の話です。将来の共通テスト情報科目でも重要視される情報リテラシーを、幼児期から段階的に育てていくことが大切です。
幼児期に身につけたい情報モラル
3-4歳の時期では、基本的なルールを理解させることから始めます。「タブレットは1日30分まで」「使った後は元の場所に戻す」など、シンプルで守りやすいルールを設定しましょう。
この時期の子どもは、ルールの意味よりも習慣化することが重要です。毎日同じ時間に、同じ方法で使用することで、規則正しい生活リズムの一部として定着させることができます。
5-6歳になると、より具体的な情報モラルについて話し合うことができるようになります。「画面の向こうにも人がいること」「自分がされて嫌なことは他の人にもしないこと」など、相手を思いやる気持ちを育てることが大切です。
また、プライバシーの概念も少しずつ教えていきましょう。「自分の名前や住所は特別な情報」「写真を撮る時は相手に許可をもらう」など、年齢に応じて理解できる範囲で説明します。
間違いを犯しても大丈夫な環境を作ることも重要です。子どもが失敗した時に叱るのではなく、一緒に解決方法を考えることで、自分で判断する力を育てることができます。
親子で学ぶデジタルマナー
デジタルマナーは、子どもだけでなく親も一緒に学んでいく必要があります。大人がお手本を示すことで、子どもはより自然にマナーを身につけることができます。
スマートフォンの使い方を例にとると、食事中や会話中にスマートフォンを触らない姿勢を大人が見せることが大切です。「今は家族の時間だから、スマートフォンはお休み」と言葉で説明しながら実践することで、場面に応じた使い分けを教えることができます。
写真撮影のマナーも重要です。人を撮影する前に「写真を撮ってもいい?」と確認する習慣を親子で身につけましょう。また、撮影した写真をSNSに投稿する際の注意点も、子どもの成長に応じて段階的に教えていく必要があります。
時間管理については、キッチンタイマーやスマートウォッチを活用して、視覚的に残り時間が分かるようにすることが効果的です。「あと5分だね」「時間になったらタブレットさんもお休みしようね」と、機器を人格化することで親しみやすく伝えることができます。
家族全員でデジタル機器を使わない時間を作ることも大切です。夕食時や就寝前の1時間など、みんなでルールを決めて実践することで、デジタルとアナログのバランスを保つことができます。
セキュリティ意識の芽生え
幼児期からセキュリティ意識を育てることは、将来のデジタル社会で安全に生活するために必要不可欠です。ただし、不安を煽るような教え方ではなく、楽しく学べる方法を工夫することが重要です。
パスワードの概念を教える際は、「秘密の合言葉」として説明すると理解しやすくなります。家族だけが知っている特別な言葉として、大切に守る意識を育てることができます。
誕生日や名前など、他の人に簡単に推測されるような情報は使わないことを、簡単な例を使って説明しましょう。「もしパスワードが『たろう』だったら、お友達にもすぐ分かっちゃうよね」といった具体的な説明が効果的です。
知らない人との接触については、リアルな世界でのルールと同じように教えることが大切です。「知らない人についていかない」「困った時は大人に相談する」といった基本的なルールを、デジタル世界にも適用できるよう説明しましょう。
年齢に応じた段階的な学習を心がけ、子どもの理解度に合わせて内容を調整することが重要です。完璧を求めるよりも、継続的に学習できる環境を整えることが、長期的な成果につながります。
データ活用能力の基礎
共通テスト情報科目では、データを適切に収集、整理、分析、活用する能力が重要視されます。これらの能力は幼児期から日常生活の中で自然と育むことができます。観察力、分類能力、比較能力など、データ活用の基礎となるスキルを遊びながら身につけることが可能です。
身の回りのデータに気づく力
幼児期の子どもたちは、自然な観察者です。この特性を活かして、身の回りにあるさまざまなデータに気づく力を育てていきましょう。
天気の観察は最も身近で継続しやすい活動です。毎日の天気を記録することで、データの蓄積と 傾向の発見を体験できます。「今日は雨だね」「昨日は晴れだったね」「雨の日が3日続いているね」といった気づきを大切にしましょう。
身長・体重の測定も優れたデータ活用学習です。定期的に測定し、記録することで、数値の変化や成長の実感を得ることができます。グラフ用紙に点を打って線で結ぶことで、視覚的に変化を捉える力も育まれます。
家族の好み調査では、「好きな食べ物」「好きな色」「好きな動物」などを調べて、データ収集の基本を学ぶことができます。家族みんなで楽しみながら、質問の作り方や回答の整理方法を身につけることができます。
時間の記録も重要な学習要素です。「朝起きる時間」「夜寝る時間」「歯磨きにかかる時間」など、日常的な行動を時計を使って測ることで、時間という数値データに慣れ親しむことができます。
分類・整理する楽しさ
データ活用の基本は、分類と整理です。これらのスキルは、おもちゃの片付けや日常の整理整頓を通じて自然と身につけることができます。
おもちゃの分類遊びでは、色別、大きさ別、種類別など、さまざまな基準で分けることができます。最初は一つの基準だけで分類し、慣れてきたら「赤くて大きいブロック」のように複数の条件で分類してみましょう。
洗濯物の仕分けは家事の手伝いをしながら学習できる実践的な活動です。「お父さんの服」「お母さんの服」「自分の服」に分けることから始めて、さらに「上着」「ズボン」「靴下」といった細かな分類まで発展させることができます。
図書館での本探しでは、分類システムを体験的に学ぶことができます。「絵本コーナー」「科学の本コーナー」「料理の本コーナー」など、本が系統立てて整理されていることに気づかせることで、情報整理の重要性を理解させることができます。
お買い物での商品分類も優れた学習機会です。スーパーマーケットで「野菜売り場」「肉売り場」「お菓子売り場」に商品が分かれていることを観察し、効率的な配置の意味を考えることができます。
比較・分析の基礎
データを活用するためには、比較・分析する能力が不可欠です。幼児期から身近な事象を比較することで、この能力の基礎を築くことができます。
大きさ比べは最も基本的な比較活動です。「どっちが大きい?」「どっちが長い?」といった質問から始めて、定量的な比較へと発展させていきましょう。定規やメジャーを使って実際に測ることで、客観的な判断の重要性を理解できます。
数量比較では、「どっちが多い?」「どっちが少ない?」といった判断から始めます。実際に数を数えることで確認し、予想と結果の違いについて話し合うことが大切です。
時間比較も重要な学習要素です。「歯磨きとお着替え、どっちが早く終わる?」「公園まで歩くのと、おうちでお絵描きするの、どっちが長い時間?」など、体感時間と実際の時間の違いを体験させましょう。
簡単なグラフ作りにも挑戦してみましょう。家族の身長を棒グラフで表したり、一週間の天気を記号で記録したりすることで、データの視覚化の基礎を学ぶことができます。最初は簡単な形から始めて、徐々に複雑な表現方法を覚えていけば十分です。
将来に向けた学習環境の整え方
共通テスト情報科目に対応するためには、幼児期から継続的な学習環境を整えることが重要です。しかし、詰め込み教育ではなく、子どもの興味・関心を大切にしながら、自然と学習できる環境を作ることがポイントです。長期的な視点で、子どもの成長に合わせて段階的にサポートしていきましょう。
家庭学習環境の作り方
専用の学習スペースを設けることから始めましょう。リビングの一角でも構いませんので、子どもが集中して作業できる場所を確保します。大切なのは、いつでも同じ場所で学習できる安定感です。
学習スペースには、アナログとデジタルの両方の教材を準備しましょう。クレヨン、色鉛筆、ノート、定規などの基本的な文房具と、年齢に応じたタブレットやパソコンを適切に配置します。
時間管理ツールも重要です。キッチンタイマーや砂時計を活用して、時間を意識した活動ができるようにしましょう。「10分間で片付けをしよう」「15分間で絵を描いてみよう」など、時間を区切った活動は集中力向上にも効果的です。
作品展示スペースを設けることで、子どもの達成感と継続意欲を高めることができます。冷蔵庫や壁面に、子どもが作った作品や記録したデータを飾ることで、学習の成果を実感できるようになります。
図書コーナーも整備しましょう。情報科目に関連する絵本や図鑑を手の届く場所に置くことで、自発的な学習を促すことができます。最新のデジタル技術を扱った子ども向けの本も積極的に取り入れましょう。
学習習慣の定着方法
規則正しい生活リズムの中に、自然と学習時間を組み込むことが大切です。「朝ごはんの後は30分間お勉強タイム」「夕食前は片付けと明日の準備」など、毎日同じ時間に同じことをする習慣を作りましょう。
小さな目標設定から始めることが重要です。「今日は10まで数えよう」「今日は赤いものを5つ見つけよう」など、達成しやすい目標を設定し、成功体験を積み重ねることで学習への意欲を高めることができます。
親子で一緒に学ぶ時間を作ることも効果的です。大人も一緒に新しいことを学ぶ姿勢を見せることで、子どもは学習することの楽しさを実感できるようになります。
記録をつける習慣を身につけさせましょう。簡単な日記や観察記録を書くことで、継続する力と振り返る力を育むことができます。最初は絵だけでも構いませんし、親が代筆してあげても問題ありません。
失敗を恐れない環境を整えることが何より重要です。間違いを叱るのではなく、「次はどうしたらいいかな?」と一緒に考える姿勢を示すことで、子どもは挑戦する勇気を持ち続けることができます。
長期的な学習計画
共通テスト情報科目を見据えた学習は、マラソンのようなものです。短期間で成果を求めるのではなく、長期的な視点で子どもの成長を見守ることが大切です。
年齢別の目標設定を行いましょう。0-2歳では観察力と好奇心、3-4歳では基本的なルールと簡単な操作、5-6歳では論理的思考と創造性というように、段階的な成長を意識した計画を立てます。
定期的な見直しも必要です。3ヶ月に一度程度、子どもの成長に合わせて学習内容や方法を調整しましょう。無理に進めるよりも、子どものペースを尊重することが長期的な成功につながります。
多様な学習機会を提供することも重要です。家庭での学習だけでなく、科学館やプログラミング教室、ロボット体験イベントなど、外部の学習機会も積極的に活用しましょう。
他の保護者との情報交換も有効です。同年代の子どもを持つ保護者と情報を共有することで、新しい学習方法や教材について知ることができます。ただし、他の子どもと比較するのではなく、参考程度に留めることが大切です。
将来の変化に対応できる柔軟性を育てることも忘れてはいけません。技術は日々進歩しており、今後新しい学習方法や評価方法が生まれる可能性があります。基礎的な思考力と学習する姿勢を身につけていれば、どのような変化にも対応できるはずです。
親自身も継続的に学習する姿勢を持つことが重要です。デジタル技術や教育方法について最新の情報を収集し、子どもと一緒に成長していく意識を持ちましょう。
まとめ:今から始める共通テスト情報対策
共通テスト情報科目の導入は、日本の教育における大きな転換点です。この変化を不安に感じる保護者も多いかもしれませんが、適切な準備を行うことで、子どもたちは確実に対応できるようになります。
0歳から6歳という幼児期は、将来の学習基盤を築く貴重な時期です。この時期にデジタルリテラシー、プログラミング的思考、情報モラル、データ活用能力の基礎を育てることで、共通テスト情報科目への対応力が自然と身につきます。
重要なのは、特別な教育を行うことではありません。日常生活の中での遊びや体験を通じて、楽しみながら必要なスキルを育てることが最も効果的です。
親子で一緒に学ぶ姿勢を大切にし、子どもの興味や関心を尊重しながら、長期的な視点で成長を見守ることが成功の鍵となります。
技術の進歩は著しく、10年後、15年後の社会がどのような姿になっているかは誰にも分かりません。しかし、基礎的な思考力と学習する意欲を身につけた子どもたちは、どのような変化にも柔軟に対応できるはずです。
今から始める小さな取り組みが、子どもたちの輝かしい未来につながることを信じて、一歩ずつ歩んでいきましょう。共通テスト情報科目は決して恐れるものではなく、子どもたちが現代社会で活躍するための重要なステップなのです。
※こちらの記事を読まれている方は、以下の記事もおすすめです。
共通テスト対策【2026年度対応】科目別の勉強法を東大卒ライターが徹底解説